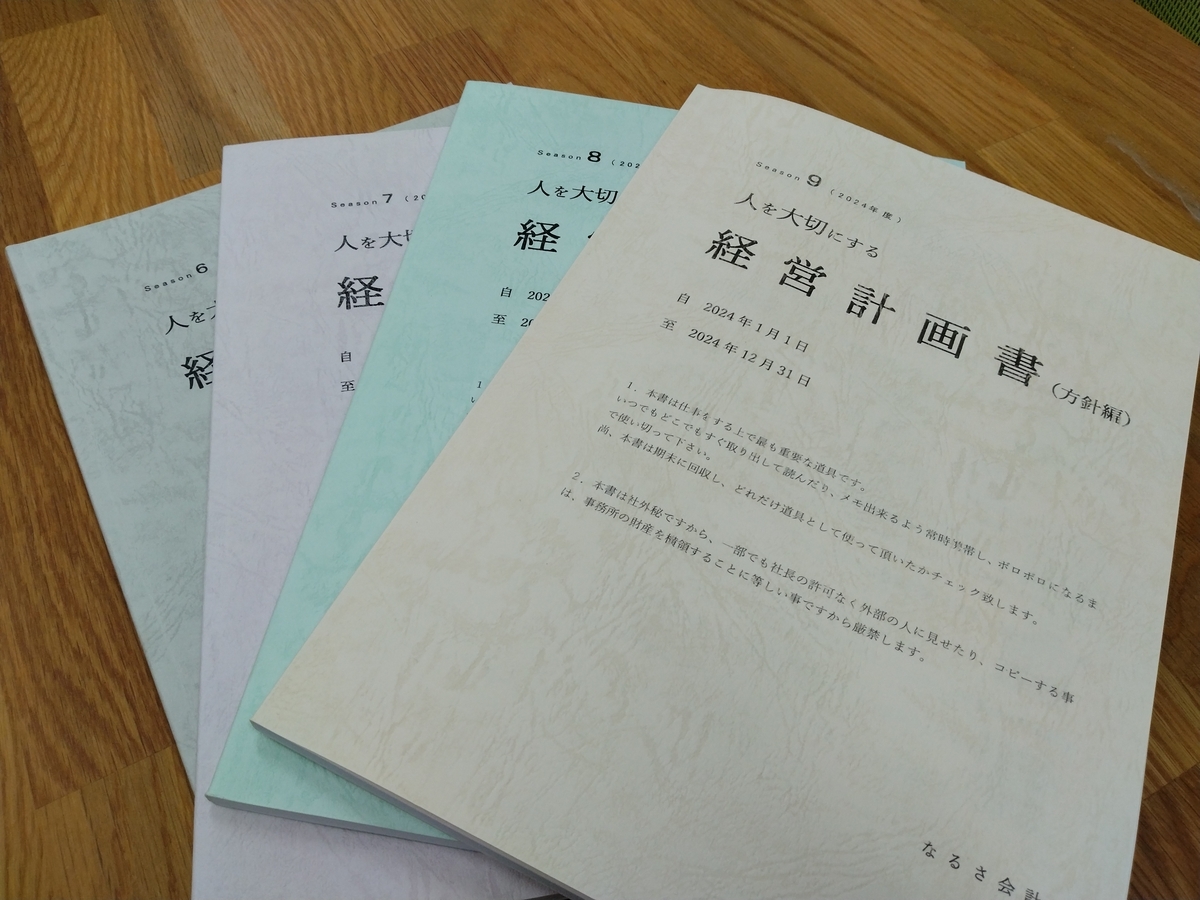2022版を作成しました
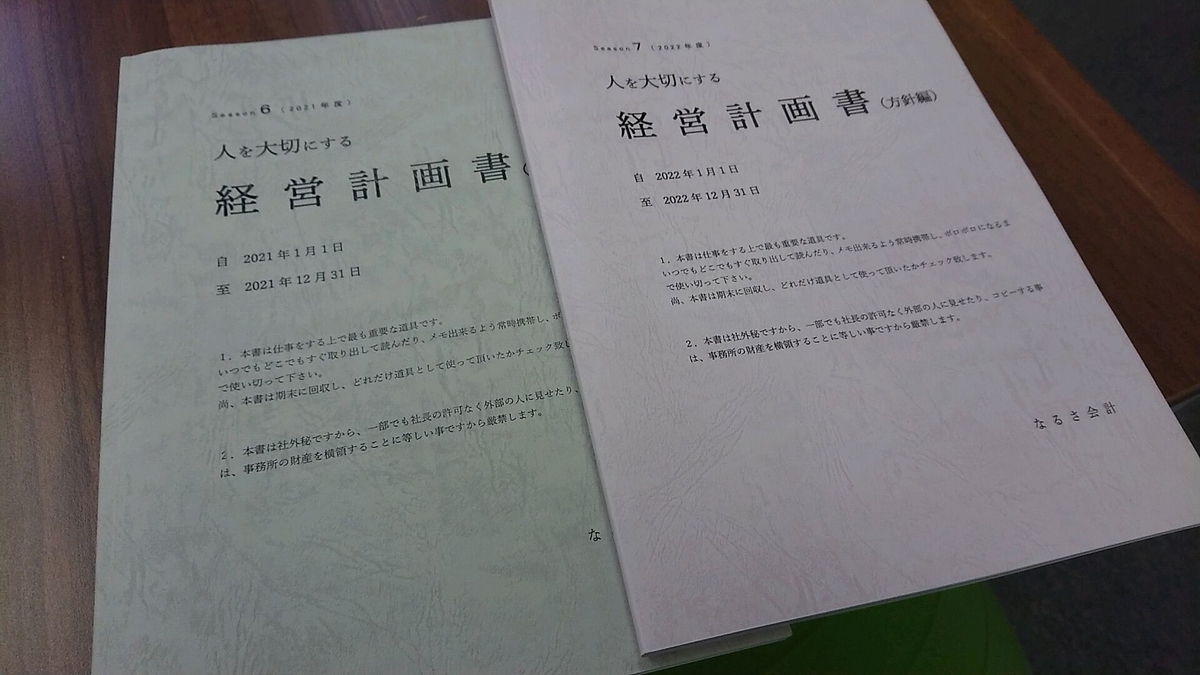
毎年、仕事始めに原稿チェックし、製本に出して翌日完成するというのがいつもの流れです。
経営計画書の中で自分がいいと思うのは中期経営計画です。
今年の目標、2年、3年先の目標が明確になり、自然とその目標を達成しようとします。
おかげさまで2016年11月に開業して連続して増収増益です。
2020年がいろいろあり、この年の収入がかなり大きかったので、2021年はさすがに上回るのは無理だろうと思っておりました。
でも、やはり頭の中に2020年の数字が残っており、どうすれば上回るのかを自然と考えるように!
そして、不思議なことにそんな考えを持っていると、仕事の流れがその方向に向くというか、いい流れになったりします。
経営計画書をガッチリ作るのは大変だろうと思います。
まずは簡単な中期経営計画を立ててみませんか?
きっと経営に役立つと思います!
経営の指標

中小企業の経営者が、毎期毎期の目標をどうするかというのは、決算の際に考えるかと思います。
来期は売上110%!とか、経常利益1億達成!などなど。
目標は立てやすいですが、いざ、事業年度が始まってから、どのような数字を気にされていますか?
稲森さんが売上高経常利益率10%を達成させなさいと言っておりますが、達成できてますか?
売上高経常利益率は、『経常利益÷売上高』です。
この算式、全社共通で活用できる指標でしょうか?
経常利益までの流れは、売上から売上原価を引いて売上総利益(粗利益)が算出され、売上総利益(粗利益)から販売費一般管理費を引いて営業利益が算出され、営業利益に営業外収益・費用が加味されて経常利益が算出されます。
問題となるのは粗利益率です。
それぞれの会社ごとに粗利益率というものは違ってきます。
100%の会社もあれば、50%の会社もあります。
粗利益率が違うと、売上高を用いて指標を計算した時、会社ごとに結論が変わってきます。
例えば、経常利益1000万円、販売費一般管理費5000万円、粗利益6000万円とします。
粗利益6000万円で、粗利益率100%の会社の売上高は?
粗利益6000万円で、粗利益率50%の会社の売上高は?
100%の場合、6000万円で、50%の場合、1億2000万円になるかと思います。
販売費一般管理費と計上利益がまったく一緒ですが、この売上高で売上高経常利益率を計算すると、16%と8%になります。
売上高経常利益率は会社によって違うんです。
その会社にあった経営指標をいうものがあり、当職は月次決算の際にご案内させていただいております。

こういった指標が参考になればと思っております。
営業利益?経常利益?②

中小企業が気にすべき利益は?
経常利益です。
中小企業レベルですと、資金運用での財務活動による利益というものはほとんどありません。
営業外収益の内容は、受取利息が少々あって、あとは雑収入といった感じではないですか?
今はコロナの影響もあって、雑収入が多少膨らんでいるかとは思いますが、基本的にはそこまで大きな金額にはならないかと思います。
営業外収入はさほどなく、営業外費用はほとんどの会社が毎期計上しております。
その内容は支払利息(借入金利息)です。
支払利息は財務活動により生じる費用のため、計上区分は営業外費用となるのが一般的です。
表示場所が違うからといっても、毎期毎期計上されるものであり、販売費一般管理費と同様な経費と考えてもおかしくありません。
なので、中小企業は経常利益を意識して経営をしていかなければならないのです。
今後の事業計画をたてる際、売上高や販管費のみを考慮していませんか?
営業外損益も考慮し、経常利益がいくらになるのかという点を意識してみて下さい。
会社の固定費は、
販売費一般管理費-営業外収入+営業外費用
です。
損益分岐点を計算する際には、この固定費を用いていただければと思います。

月次決算書、社長の成績表では、固定費や損益分岐点などの経営に役立つ指標をご覧いただけます。
社長の成績表に関しては、前2期分の決算書をいただければ無料で作成させていただきますので、気になった方はお問い合わせください。
営業利益?経常利益?

損益計算書には、5つの利益があります。
売上総利益、営業利益、経常利益、税引き前利益、当期利益です。
銀行さんが気にする利益は?
銀行さんは営業利益を気にします。
なぜなら、お金を貸すのに、返済できるかどうかだけが関心事だからです。
債務償還年数や、インタレスト・カバレッジ・レシオなどの指標は、営業利益をもとに計算されるという点でおわかりいただけると思います。
営業利益は工夫によってうまく『操作』できます。
販売費一般管理費に計上しているものを、営業外費用または特別損失に計上したり、雑収入に計上しているものを、売上高もしくは販売費一般管理費のマイナス項目として計上したりすることにより、営業利益はその会社最大のものを表示できます。
そんな工夫に気づく経営者はなかなかいません。
会社の決算書を眺めてみて下さい。
販管費に役員の保険料や、退職引当金、特別修繕引当、雑収入に社宅家賃などありませんか?
それらは工夫によって営業利益を改善できる要素です。
そんな提案を毎月の月次決算でさせていただいております。

お問い合わせはお気軽に。
経常利益は、会社の運営をどのように行ったかによって
値引き戦略

コロナの影響で、商品が今まで通りに売れないなんて状況ではないでしょうか?
そんな時、値引きをしなければならない状況に陥ることも多々あるかと思います。
ただでさえ苦しいのに、さらに値引きなんて・・・。
今回は値引きについて考えたいと思います。
どの会社でも原価率は一定の数値を持っていると思います。
一般的には卸売業の原価率は90%、小売業の原価率は80%などの指標があります。
値引きはしていいの?ダメなの?
その判断は粗利益率が高いか低いかによって変わってきます。
粗利益率が高い会社(=原価率が低い会社)
売上高 1億円
売上原価 2千万円(20%)
粗利益 8千万円(80%)
固定費 5千万円
経常利益 3千万円(30%)
この会社が10%の値引きをした場合
売上高 9千万円
売上原価 2千万円(22%)
粗利益 7千万円(78%)
固定費 5千万円
経常利益 2千万円(20%)
経常利益は確保できます。
粗利益率が低い会社(=原価率が高い会社)
売上高 1億円
売上原価 7千万円(70%)
粗利益 3千万円(30%)
固定費 2千万円
経常利益 1千万円(30%)
この会社が10%の値引きをした場合
売上高 9千万円
売上原価 7千万円(78%)
粗利益 2千万円(22%)
固定費 2千万円
経常利益 0千万円(0%)
経常利益が確保できません。
固定費が違うからこの比較はおかしいのでは?と思われる方もいるかもしれません。
ですが、固定費÷粗利益額は0.625と0.666なので、粗利益で賄っている固定費の割合はそこまで違わないんです。
ですが、結論には大きな差が生じます。
粗利益率が高い会社は値引きの戦略を実行しても大丈夫です。
粗利益率の低い会社は値引き戦略に参戦してはいけません。
では、粗利益率が低い会社はどうすべきか?
ここまで『率』に注目していましたが、粗利益率の低い会社は粗利益額を守るように心がけてください。
値引きをしても、今まで以上に数を売ることができれば、同じだけの粗利益額を稼ぐことができます。
固定費は一定なので、粗利益額をキープできたのであれば、今まで通りの経常利益を稼ぐことができます。
『3個セットで990円』なんてセット売りを良く見かけませんか?
これも、値引きをしつつ、販売数を減らさない努力です。
単価 × 数量 = 売上
単価を下げる戦略が値引きですが、数量という視点からも戦略はあります。
売上がどのように構成されているかをもう一度考え直してみてください。
月次決算でこのようなお話をさせていただいております。

お気軽にお問い合わせください。